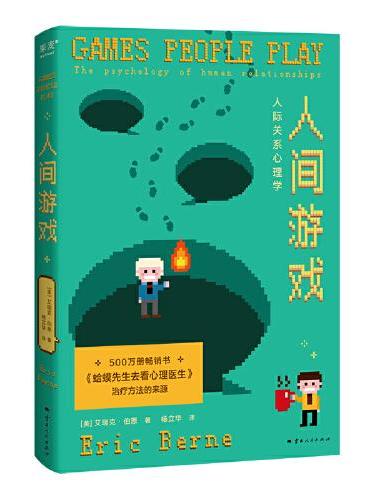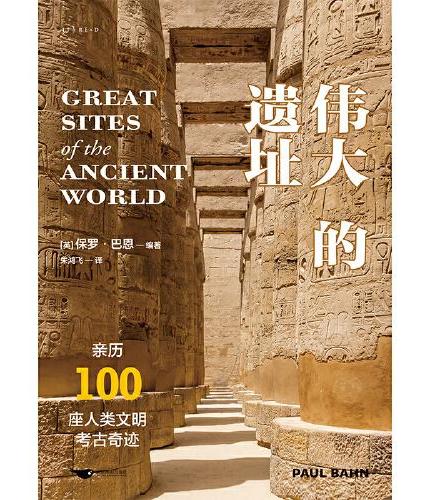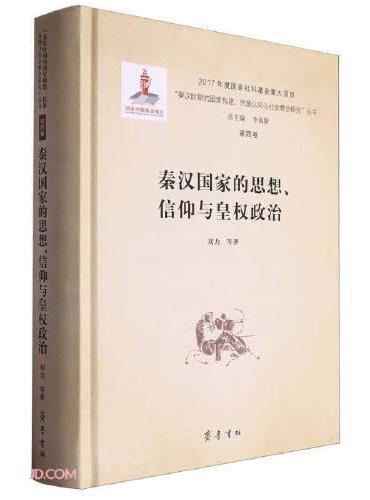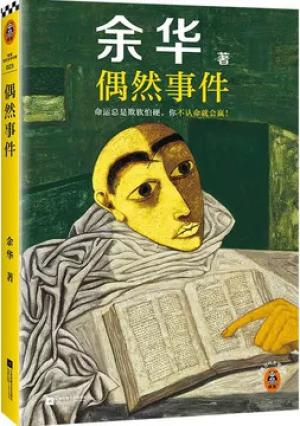新書推薦:
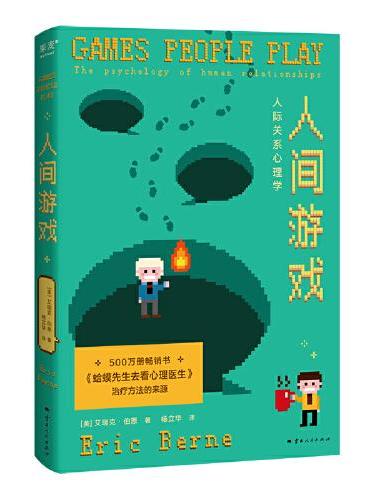
《
人间游戏:人际关系心理学(500万册畅销书《蛤蟆先生》理论原典,帮你读懂人际关系中那些心照不宣的“潜规则”)
》
售價:HK$
43.8
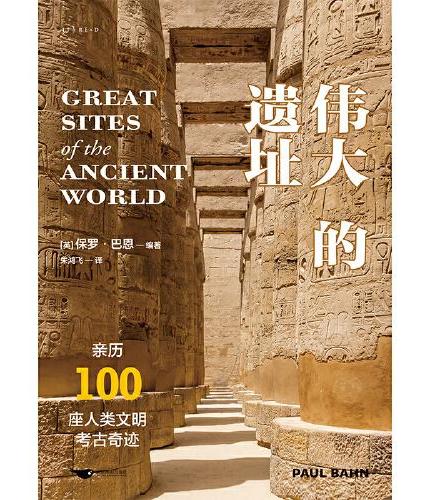
《
伟大的遗址(亲历100座人类文明考古奇迹)
》
售價:HK$
206.8
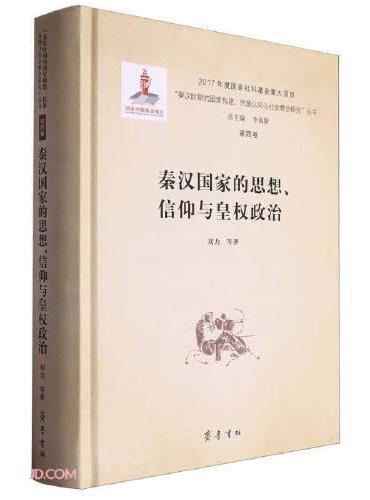
《
秦汉国家的思想、信仰与皇权政治
》
售價:HK$
215.6

《
反卷社会:打破优绩主义神话(一本直面焦虑与困境的生活哲学书!)
》
售價:HK$
83.6
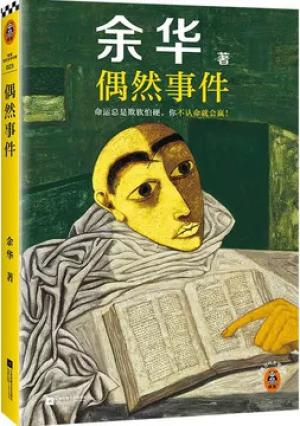
《
偶然事件(命运总是欺软怕硬,你不认命就会赢!)
》
售價:HK$
54.9

《
余下只有噪音:聆听20世纪(2025)
》
售價:HK$
206.8

《
如何将知识转化为行动
》
售價:HK$
76.8

《
助人技术本土化的刻意练习
》
售價:HK$
87.9
|
| 編輯推薦: |
|
本书以《数理精蕴》为例,阐述了中国翻译的西学译著对日本文化的影响。
|
| 內容簡介: |
|
本书稿是对中国西学书籍《数理精蕴》(1722年)及与之相关的其他中国、朝鲜、欧洲书籍在日本的传播史进行的文献学研究。由考论篇写本研究篇两部分构成。 考论篇中解决了(1)日本最早对数表的原典;(2)《数理精蕴》是否存在完整和译本;(3)朝鲜书籍与《数理精蕴》在日本传播的关系等三个日本学术界长期悬而未决的问题。另外还论述了早期中译数学术语对日本影响的问题。 写本研究篇中对江户后期出现的《数理精蕴》写本(如延冈藩藏《数理精蕴解》写本、大阪和算学校写本、长崎海军传习所写本等)进行目录学、文献学的整理与梳理,比较各写本的异同。通过写本分析指出《数理精蕴》在日本近代数学教育史上的启蒙性意义。 中文目录 前言 上篇 考论篇 第一章:《数理精蕴》与江户后期日本的对数 第一节:研究史 第二节:《数理精蕴》中的对数原理 第三节:对数表与八线对数表的区别 第四节:鹤山樵夫《数理精蕴补解》的文献学调查 第五节:安岛直圆《不朽算法》与《数理精蕴补解》的比较 第六节:延冈藩藏书《数理精蕴解》中对数比例解研究 小结 第二章:荷兰语图书与江户后期日本的对数 第一节:研究史 第二节:荷兰书《航海宝函》的文献调查 第三节:《航海宝函》中的达维斯对数表 第四节:本多利明《大测加减代乘除表》典据研究 小结 第三章:《数理精蕴》日本传来时期考 第一节:研究史 第二节:《数理精蕴》日本传来时期考 小结 第四章:《数理精蕴》中的数学术语 第一节:研究史 第二节:《数理精蕴》中的数学术语 第三节:《数学精蕴》术语表 小结 第五章:志筑忠雄的日译数学术语 第一节:从中日传统典籍中的继承 第二节:志筑忠雄的译词 第三节:三角对数与割圆八线的相关术语 第四节:志筑忠雄的数学术语对照表 小结 下篇 写本研究 第六章:日本文化年间延冈藩《数理精蕴解》的文献研究 第一节:文献调查 第二节:内容与特征 第三节:《数理精蕴解》中的比例规及其原理 小结 第七章:金武良哲《数理精蕴》写本研究 第一节:金武良哲略传 第二节:金武写本上篇内容 第三节:金武写本下篇内容 小结 第八章:福田家《数理精蕴》写本研究 第一节:文献调查 第二节:写本考察 小结
|
| 關於作者: |
|
李文明,中国社会科学院世界历史研究所助理研究员,在南开大学取得学士、硕士学位,在日本京都大学取得博士学位。主要研究日本江户时代文化史、日本欧洲文化交流史。
|
| 目錄:
|
目次
第一部論考編
第一章:和算家の対数受容
第一節:研究史
第二節:『数理精蘊』の対数理論
第三節: 対数表と八線対数表の区別
第四節:鶴山樵夫『数理精蘊解』の書誌調査
第五節:安島直円『不朽算法』と『数理精蘊補解』の比較
第六節:延岡藩『数理精蘊解』「対数比例解」の研究
小括
第二章:蘭書による対数受容
第一節:研究史
第二節:蘭書『航海宝函』の調査
第三節:『航海宝函』中ダウウェス対数表
第四節:本多利明『大測加減代乗除表』典拠考
小括
第三章:『数理精蘊』日本伝来時期考
第一節:研究史
第二節:『数理精蘊』日本伝来時期考
小括
第四章:漢訳数学書の用語
第一節:研究意義および研究史
第二節:『数理精蘊』の数学用語の典拠
第三節:『数理精蘊』の数学用語表
小括
第五章:江戸後期の和訳洋書中の数学用語
第一節:和漢典籍からの継承
第二節:志筑忠雄の創出
第三節:三角対数および割円八線
第四節:志筑忠雄の数学訳語対照表
小括
第二部 写本研究
第六章:文化年間延岡藩内藤家本『数理精蘊解』
第一節:書誌調査
第二節:内容特徴
第三節:『数理精蘊解』中の比例規の原理および用法
小括
第七章:金武良哲『数理精蘊』写本研究
第一節: 金武良哲の略伝
第二節:『数理精蘊』写本上編写本の内容
第三節:『数理精蘊』写本下編写本の内容
小括
第八章:福田家『数理精蘊』写本研究
第一節:書誌調査.
第二節:写本考察
小括
|
| 內容試閱:
|
『数理精蘊』は、江戸時代の日本にも輸入された。近代以来の数学史研究は、江戸時代における『数理精蘊』の影響に触れてはいるが、なお以下の疑問を残している。
①『数理精蘊』の輸入時期
②『数理精蘊』の和訳本および和訳年
③『数理精蘊』と対数の輸入との関係
この三つの問題は、いずれも関連するものである。『数理精蘊』の最大の特徴は、対数表製法を収録していることである。『数理精蘊』以外の漢訳書に、対数表製法はない。そのため、江戸時代の対数書の典拠が究明されれば、『数理精蘊』の輸入時期もより明確になる。
本論は、天明?寛政期の日本最古の対数書から論述を始める。そして享和?寛政期の対数書の典拠および『数理精蘊』との関係を明らかにしようと思う。更に、『数理精蘊』の輸入時期およびその和訳年という問題を考察する。
本論は、文献学?書誌学的な研究手法をもちいて、書誌調査および文献解読にもとづいた研究をおこなう。
文献解読中、漢訳書および和訳書の中の数学用語も、筆者の視野に入った。当然、数学用語の範囲は広く、その数も多い。本論は、『数理精蘊』を中心に、近世日本と中国で使われた数学用語を整理し、その起源を文献学的に解明しようとする。
|
|